画像の下に内容をテキスト化した
ページがございます。
こちらをクリックしてください
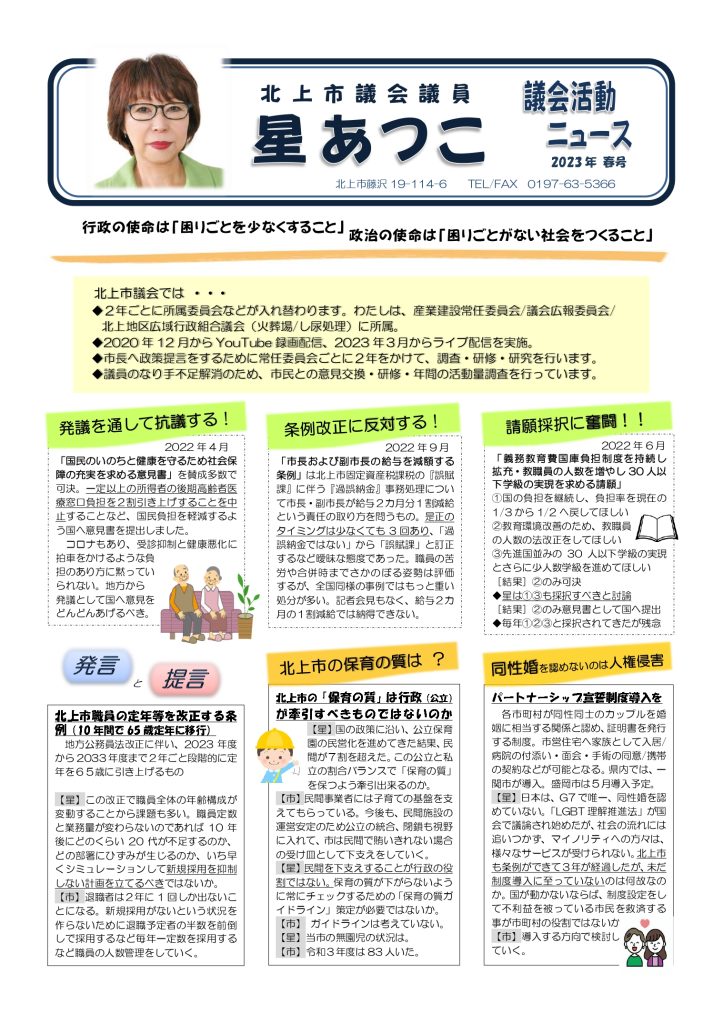


行政の使命は
「困りごとを少なくすること」
政治の使命は
「困りごとがない社会をつくること」
北上市議会では ・・・
◆2年ごとに所属委員会などが入れ替わります。わたしは、産業建設常任委員会/議会広報委員会/北上地区広域行政組合議会(火葬場/し尿処理)に所属。
◆2020年12月からYouTube録画配信、2023年3月からライブ配信を実施。
◆市長へ政策提言をするために常任委員会ごとに2年をかけて、調査・研修・研究を行います。
◆議員のなり手不足解消のため、市民との意見交換・研修・年間の活動量調査を行っています。
発議を通して講義する!2022年4月
「国民のいのちと健康を守るため社会保障の充実を求める意見書」を賛成多数で可決。
一定以上の所得者の後期高齢者医療窓口負担を2割引き上げすることを中止することなど、国民負担を軽減するよう国へ意見書を提出しました。
コロナもあり、受診抑制と健康悪化に拍車をかけるような負担のあり方に黙っていられない。
地方から発議として国へ意見をどんどんあげるべき。
2023.3議会報告会報B4表_page-0001.jpg)
条例改正に反対する!2022年9月
「市長および副市長の給与を減額する条例」は北上市固定資産税課税の『誤賦課』に伴う『過誤納金』事務処理について市長・副市長が給与2カ月分1割減給という責任の取り方を問うもの。
是正のタイミングは少なくても3回あり、「過誤納金ではない」から「誤賦課」と訂正するなど曖昧な態度であった。
職員の苦労や合併時までさかのぼる姿勢は評価するが、全国同様の事例ではもっと重い処分が多い。
記者会見もなく、給与2カ月の1割減給では納得できない。
請願採択に奮闘!!
「義務教育費国庫負担制度を持続し拡充・教職員の人数を増やし30人以下学級の実現を求める請願」
①国の負担を継続し、負担率を現在の1/3から1/2へ戻してほしい
②教育環境改善のため、教職員の人数の法改正をしてほしい
③先進国並みの30人以下学級の実現とさらに少人数学級を進めてほしい
[結果]②のみ可決
◆星は①③も採択すべきと討論
[結果]②のみ意見書として国へ提出
◆毎年①②③と採択されてきたが残念
2023.3議会報告会報B4表_page-0001.jpg)
発言と提言
北上市職員の定年等を改正する条例(10年間で65歳定年に移行)
地方公務員法改正に伴い、2023年度から2033年度まで2年ごと段階的に定年を65歳に引き上げるもの
- 【星】この改正で職員全体の年齢構成が変動することから課題も多い。
職員定数と業務量が変わらないのであれば10年後にどのくらい20代が不足するのか、どの部署にひずみが生じるのか、いち早くシミュレーションして新規採用を抑制しない計画を立てるべきではないか。 -
【市】退職者は2年に1回しか出ないことになる。
新規採用がないという状況を作らないために退職予定者の半数を前倒しで採用するなど毎年一定数を採用するなど職員の人数管理をしていく。
北上市の保育の質は?
北上市の「保育の質」は行政(公立)が牽引すべきものではないのか
- 【星】国の政策に沿い、公立保育園の民営化を進めてきた結果、民間が7割を超えた。
この公立と私立の割合バランスで「保育の質」を保つよう牽引出来るのか。 -
【市】民間事業者には子育ての基盤を支えてもらっている。
今後も、民間施設の運営安定のため公立の統合、閉鎖も視野に入れて、市は民間で賄いきれない場合の受け皿として下支えをしていく。 - 【星】民間を下支えすることが行政の役割ではない。保育の質が下がらないように常にチェックするための「保育の質ガイドライン」策定が必要ではないか。
-
【市】 ガイドラインは考えていない。
- 【星】当市の無園児の状況は。
-
【市】令和3年度は83人いた。
2023.3議会報告会報B4表_page-0001.jpg)
同性婚を認めないのは人権侵害
パートナーシップ宣誓制度導入を
各市町村が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め、証明書を発行する制度。
市営住宅へ家族として入居/病院の付添い・面会・手術の同意/携帯の契約などが可能となる。
県内では、一関市が導入。
盛岡市は5月導入予定。
- 【星】日本は、G7で唯一、同性婚を認めていない。
「LGBT理解推進法」が国会で議論され始めたが、社会の流れには追いつかず、マイノリティへの方々は、様々なサービスが受けられない。
北上市も条例ができて3年が経過したが、未だ制度導入に至っていないのは何故なのか。
国が動かないならば、制度設定をして不利益を被っている市民を救済する事が市町村の役割ではないか。 -
【市】導入する方向で検討していく。
2023.3議会報告会報B4表_page-0001.jpg)
研修しました
「住民自治の根幹」としての議会 議会からの政策サイクルを学ぶ 2022年11月17日
― 大正大学 江藤俊昭教授 ―
議会改革の目的は、「形式の整備」をする事だけではなく、住民自治の推進、住民福祉の向上につなげること。
何より、住民から信頼される議会づくりをする事。
そのための手法が「議会からの政策サイクル」の確立と行動である。
議会が住民の意見を吸い上げ、議員間の討議を通じて効果的に反映させる仕組みを確立させるため、先進議会の事例を研究。
「議員」ではない「議会」という集合体。
個人の「一般質問」で終わらせずに「施策提言」としてサイクルを回していく事への転換が求められている。
[先進自治体事例紹介]
・会津若松市議会/可児市議会
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
議会が一つになって市民の声を政策に反映させることこそ議会の役割だわ!
社会福祉と動物愛護管理を考える研修会 2022年12月19日
― 成城大学 打越綾子教授 ―
◆講演「ペットの多頭飼育問題を考える」
多数の動物を飼育していて適切な飼育管理ができないことにより、
①飼養者の生活状況の悪化、
②動物の状態の悪化、
③周辺の生活環境の悪化
が生じている状況を「多頭飼育問題」といい、近年の大きな社会問題。
飼い主の生活困窮や社会福祉的な支援を必要とすることが多い。
「人の問題」と「動物の問題」として別々にとらえるのではなく、関係者が連携して対応することが重要。
環境省ではガイドラインを作成し、保健所(県)・市役所・地域・愛護保護ボランティア団体と連携し、動物の命を救いなら、飼い主の生活再建につなげていくよう指導している。
北上市も取り組もう!!
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
困難を抱える子どもの早期支援 2022年12月19日
― 岩手県立大学 櫻 幸恵教授 ―
貧困・虐待・いじめ・不登校・ヤングケアラーなど困難を抱える子どもは、たくさんいるのに見えにくい。
「助けて」と言えない、
言わない子どもたちを誰がキャッチするのか。
地域での包括的支援の仕組みが早急に必要。
ソーシャルワーカーを増員しての継続的な伴走型の取り組みが未来を拓く。
初めて令和5年4月に「子ども基本法」が子ども家庭庁の設置と共に施行される。
さらに社会全体の課題にしていこう。
司法おけるジェンダー平等がなぜ重要なのか 2023年1月14日
― 早稲田大学大学院 石田京子教授 ―
女性の政治参画が進まない。
社会の歪みが女性を押しつぶそうとしているのに、政策が追い付かない。
法律はあっても、生活を守れない。
誰もが輝ける社会…というけれど、自分はそれには含まれないと感じる。
司法(裁判所)は、国の基盤であり、多数決原理では救えない少数者の権利を保障する権限を持っている。
にもかかわらず、裁判官・検察官・弁護士のうち女性が3割に満たない現状はどのような問題をもたらしているのか。
ジェンダー平等視点が裁判の判決をも左右する現実と被害者をさらに苦しめる二次被害を防ぐという事を知るべきである。
二次被害の例:性被害の被害者に「あなたにもそうされるような原因があったかも知れないから」「我慢したらどうか」など
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
議会内での調査研究
〈議員のなり手不足解消について〉◆議員報酬及び定数について
― 大正大学 江藤俊昭教授 ―
◆議員報酬や定数は、住民の福祉向上を実現するための議論でなければならない。
◆定数は、決定する根拠が不明確。
◆市民から「報酬を上げたのだから定数を減らせ」と叩かれるが、議会は報酬と連動させて受け入れるような単純な機関であってはならない。
◆定数を減らせば、当選ラインが上がり、議会の門戸を狭める。そのことは社会の多様性を重視する動きに逆行し、当然、議員のなり手不足を加速させる。
◆定数を減らすことは、市民のためにはならない。
◆全国の先進議会の取り組みが成果を上げているように、市民と一体となっての政策提言や予算への反映、議会運営の「見える化」は不可欠。「福祉向上のために議会が必要だ」と市民に信頼されるよう合議体としての議会を成熟させる様々な改革に取り組む事が急務。
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
視察に行きました
〈 新潟県三条市 〉産業建設常任委員会
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
37歳の市長です!先進国で導入している経済指標(市民の所得)とウェルビーイング指標(労働者の幸せ度)の同時到達をまちの目指す姿と位置づけています!!
◆全国的、世界的にも「ものづくりのまち」として有名。「中小企業の経営に対する市の支援、後継者育成及び人材確保に係る支援について」を中心に現状や課題、今後の対応など研修。
◆人口、面積、世帯数、農工都市という形態など当市と類似しているが、単なる後継者確保ではなく、伝統工芸士を含めた鍛冶職人の「技」と「人」の二つを兼ね合わせた担い手を育成していく必要がある点が当市とは大きく異なる。
◆力のある強い企業だけが生き残る仕組みでは、伝統技術は継承できない。
◆中小企業の地場産業を維持していくためには、行政と企業が一体的に事業を進め、全体の底上げを図ることが重要である。
◆少子化、近年若者の流出、後継者不足などはどの自治体でも喫緊の課題であり、有効求人倍率や給与水準がいくら良くても個人の幸福度に直結しなければ人は定住しない。子育て・若者政策や福祉向上と福利厚生も共に充実させることが重要だという事を企業や市民に徹底周知させることが行政の大事な任務である。
◆今後の大学卒業生の進路などを参考に、中小企業を支える取り組みをぜひ取り入れていきたいと思う。
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
ペットの命も大切にする先進都市になってほしいよね
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
こどもを大切にすると国や街が発展していくんだね
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
議会も成長して市民から身近で信頼されるようにならなければね
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
2023.3議会報告会報B4裏訂正版_page-0001.jpg)
生きにくいと感じる人が多く集まれる街にしたいね

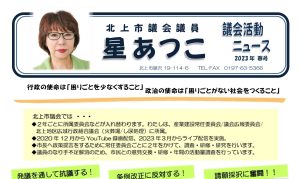
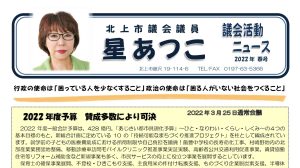
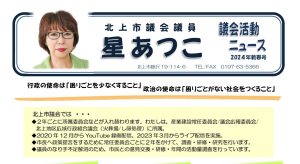
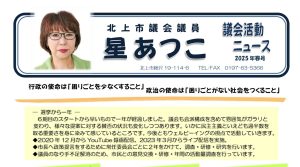
2021.3議会報告会報B4表_page-0001-300x161.jpg)
